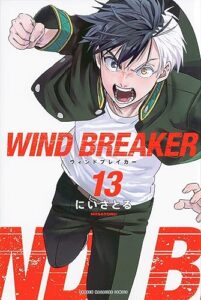📝 この記事のポイント
- 久々に会った友人が激やせしていて、「大丈夫? 」と聞いたらダイエット成功とのこと。
- 聞けば、半年前からパーソナルジムに通い始めたらしい。
- 食生活もがらりと変えたと、ツルツルになった肌で得意げに話す。
久々に会った友人が激やせしていて、「大丈夫?
」と聞いたらダイエット成功とのこと。
聞けば、半年前からパーソナルジムに通い始めたらしい。
週に二回、自分を追い込む時間。
食生活もがらりと変えたと、ツルツルになった肌で得意げに話す。
彼の目は、以前の覇気のないそれとはまるで違っていた。
なんというか、こう、妙に輝いている。
「お前もどうだ? すごくいいぞ。俺、生まれて初めて運動が楽しいって思ったもん」
そう言われても、私は生返事を返すのが精一杯だった。
運動、ねえ。
それは私にとって、まるで夏休みの宿題の最終日にまとめてやる作業のようなものだ。
気が重く、始めるまでに時間がかかり、終わったところで達成感よりも疲労感が勝る。
そして、なぜかいつも完璧には終わらない。
中学、高校と、私は部活に真面目に取り組んでいた。
いや、取り組まざるを得なかった、が正しいかもしれない。
体育会系の部活特有の、あのピリピリした空気。
タイムを測るたびに「遅い!
」と怒鳴られ、先輩の視線に怯えながら練習に励む日々。
目標は常に「より早く」「より強く」で、自分の体が今、どう感じているかなんて、考える余裕もなかった。
むしろ、感じてはいけない、とさえ思っていた節がある。
少しでも疲れた素振りを見せれば「気合が足りない」と一蹴されるのがオチだ。
そんな毎日を過ごしているうちに、私の体はすっかり運動嫌いになってしまった。
部活を引退した時の解放感は、今でも鮮明に覚えている。
あれは、義務からの解放、という他ない。
それ以来、私は自ら進んで運動するという行為から遠ざかってきた。
体育の授業は最低限にこなし、大人になってからは、たまに散歩するくらいが関の山。
それでも特に不便を感じることもなく、休日は恋人と美味しいものを食べに出かける生活を満喫していた。
だから、友人の目の輝きを目の当たりにしても、すぐに「私も!
」とはならなかった。
しかし、同時に、彼の変化を少しだけ羨ましいと感じたのも事実だ。
なんというか、自分の体と向き合って、それを変えていく姿は、純粋に格好いい。
そして、楽しそうだった。
その日の夜、同棲している恋人に友人の話をした。
「へえ、すごいね」と、彼は特に興味もなさそうに、テレビを見ながらポテトチップスを食べていた。
彼は私と違って、細身で食べる量も多く、特に運動をせずとも体型を維持できる、世にも稀な体質を持っている。
ある意味で、私とは真逆の存在だ。
いや、逆だからこそ、一緒にいるのかもしれない。
「でもさ、ちょっとだけ、私も運動してみようかなって思っちゃった」
「え、まじで?
」
彼は驚いた顔をして、ポテトチップスの手を止めた。
「うん、なんとなく。
なんか、こう、自分と向き合う、みたいな?
」
「ふーん。
まあ、いいんじゃない?
彼のあっさりとした返事に、拍子抜けしつつも、私は妙な決意を固めた。
別にパーソナルジムに通うような大掛かりなことはしない。
まずは、家でできることから始めよう。
そう思って、次の休日、私と恋人は近所の大型スーパーの隣にあるスポーツ用品店へ向かった。
店内には、カラフルなウェアや、機能的なシューズ、そして様々なトレーニング器具が並んでいる。
目に飛び込んできたのは、やたらとマットな質感のダンベルだった。
鮮やかなミントグリーンと、淡いピンク。
まるでオブジェのように可愛らしい。
「これ、可愛いね」
私が指差すと、恋人も「ほんとだ。
こういうのだったら、部屋に置いてあっても邪魔にならないかもね」と、珍しく乗り気だった。
「どうせなら、ちょっと重めがいいんじゃない?
効果ありそうだし」
「でも、いきなり重いのだと続かないんじゃない?
謎の自信に満ち溢れ、私はミントグリーンの3kgのダンベルを手に取った。
ずっしりとした重みが、なんだか「ちゃんと運動してる感」を掻き立てる。
隣で恋人は、500gの可愛らしいピンクのダンベルを手に取り、「これくらいがちょうどいい」と笑っている。
おいおい、それ、パンを焼くときに使う重りか?
と心の中でツッコミを入れつつ、私も3kgのダンベルをレジへ持っていった。
家に帰り、早速ダンベルを床に置いてみた。
可愛らしいミントグリーンが、殺風景な部屋に彩りを添える。
なんだか、それだけで運動した気分になった。
その日は、ダンベルを眺めるだけで終わってしまったけれど、翌日こそは、と意気込んだ。
翌日。
意気込んだはいいものの、いざダンベルを手に取ると、どうしていいか分からない。
YouTubeで「自宅 ダンベル トレーニング」と検索し、初心者向けの動画をいくつか見てみる。
画面の中のトレーナーは、笑顔で軽々とダンベルを上げ下げしている。
「まずは、肩からゆっくりと上げていきましょう」
言われた通りにやってみるが、3kgのダンベルは、見た目以上に重い。
たった数回上げ下げしただけで、肩が悲鳴を上げた。
「うーん、これ、効いてるのかな?
」
鏡に映る自分の姿は、まるで初めて逆上がりに挑戦する子どものように、ぎこちない。
恋人は隣で、私の半分の重さのダンベルを軽々と持ち上げながら、にこやかにスクワットをしている。
なぜかちょっと腹が立った。
結局、その日も数分でギブアップ。
ダンベルは、部屋の隅に置かれたまま、私の運動意欲と共に静かに佇むことになった。
それから数週間、ダンベルはインテリアの一部と化していた。
時々、掃除の邪魔になるからと、恋人が別の場所に動かすくらいで、私が手に取ることはほとんどない。
「あのダンベル、どうしたの?
」
ある日の夕食中、恋人が突然聞いてきた。
「え、あー、あれね……」
私は言葉を濁した。
まさか、部屋の隅でホコリをかぶっている、とは言えない。
「もしかして、もう使ってない?
」
彼の目は、私の心を全て見透かしているかのように、真っ直ぐだった。
「いや、たまには、ね。
気分転換に」
苦しい言い訳だ。
自分で言っていて、顔が熱くなるのを感じた。
結局、ダンベルは、私の「運動したい」という一時的な衝動の象徴となってしまった。
あの日のスポーツ用品店での高揚感はどこへやら。
店員さんに「効果ありますよ!
」と言われて、つい買ってしまった、あの時の自分を少しだけ恨めしく思う。
でも、完全に無駄になったわけではない、と自分を慰める。たまに、本当にたまにだけど、気が向いた時にダンベルを手に取ってみる。相変わらず、数回で肩が痛くなるけれど、それでも「ちょっとだけ」は動かしている。
最近、友人に連絡してみた。
「あの後、どうなった?
」と聞かれたら、どう答えようかと思っていたら、彼の方から「最近、運動してる?
」と聞いてきた。
「うーん、まあ、マイペースにね」
「そっか。
俺もさ、最近はジムも週一くらいなんだ。
なんか、無理すると続かないって分かってさ」
彼の言葉に、私は少しだけホッとした。
そうか、無理しなくてもいいんだ。
私たち大人になった人間は、誰かに強要されるわけでもなく、誰かと競争するわけでもなく、ただ「自分のためだけに」何かをするのが、本当に難しいのかもしれない。
部活のトラウマというほど大袈裟なものでもないけれど、何かに「縛られる」ことへの抵抗感は、確かに私の中に根付いている。
先日、恋人と近所の公園を散歩している時、ふと、地面に落ちていた石を拾い上げた。
手のひらに乗るくらいの、ごく普通の石だ。
これを握って、腕を振るだけでも、少しは運動になるんじゃないか?
なんて、馬鹿なことを考えて、そっとポケットに入れた。
家に帰り、ポケットから石を取り出すと、隣にミントグリーンのダンベルが置いてある。
そうか、この石も、ダンベルも、結局は同じなんだ。
どちらも、私が「何かを始めたい」と思った時に、そっと寄り添ってくれる、ただの道具。
結局、私はあの頃の友人のように、運動で激やせしたり、体つきが劇的に変わったりすることはなさそうだ。
でも、それでいいような気がする。
休日は恋人と美味しいものを食べに出かけ、家に帰れば、部屋の隅に置かれたダンベルと、ポケットの中の石を眺める。
そして、気が向いた時に、ほんの少しだけ、体を動かす。
運動を嫌いにさせたのは、誰だったのか。
あるいは、何だったのか。
それはもう、どうでもいい。
ただ、汗を流すという行為が、誰かの評価のためでも、序列を上げるためでもなく、ただ自分自身の心と体のためだけのものになる日が、いつか来るのかもしれない。
その日を夢見ながら、今日も私は、スーパーで期間限定のスイーツを眺めている。
まあ、それも、私にとっての「運動」みたいなもの、かもしれない。
たぶん。
💡 このエッセイは、Togetterの話題から着想を得て、2026年の視点で書かれた創作記事です。