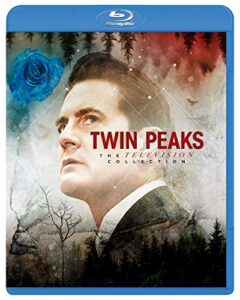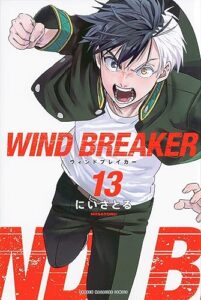📝 この記事のポイント
- カラオケで十八番を歌ったら、キーが合わなくて途中でリセットした。
- 何というか、あの曲はもう何百回も歌ってきたから、このキーで、このテンポで、この声量で歌うのが僕の中の「正しい」姿なんだよね。
- ちょっとでも違うと、全部が台無しになった気がして、ついリセットボタンに手が伸びる。
カラオケで十八番を歌ったら、キーが合わなくて途中でリセットした。
何というか、あの曲はもう何百回も歌ってきたから、このキーで、このテンポで、この声量で歌うのが僕の中の「正しい」姿なんだよね。
ちょっとでも違うと、全部が台無しになった気がして、ついリセットボタンに手が伸びる。
完璧主義というより、自分なりのこだわりが強すぎるのかもしれない。
そんな僕が、先日、まさかの「儀式」に立ち会うことになった。
その日は、シェアハウスの共有リビングで、溜まった洗濯物を畳んでいた。
当番制の夕飯は、僕の担当じゃないから気が楽だ。
冷蔵庫には、昨日の夜に半額で買ったサラダチキンがまだ残っている。
もう一人の住人であるアキラが、どこからか連れてきたらしい中学生の少年が、インフルエンザで寝込んでいる。
少年は普段からあまり口をきかないタイプで、僕らが「ゲームのやりすぎじゃない?
」とからかうと、決まってフッと鼻で笑うだけだ。
そんな彼が、熱で朦朧としながらも、掠れた声で僕を呼んだ。
「あの、プリン…」。
冷蔵庫を覗くと、先日スーパーで特売していた「プッチンプリン」が二つ残っていた。
ああ、これか。
僕も子どもの頃はよく食べたなあ、なんてノスタルジーに浸りながら、冷えたプリンを手に取り、彼の部屋へ向かった。
部屋のドアをノックすると、微かに「どうぞ」と返事があった。
少年は布団の中で顔を真っ赤にして、僕が手にしたプリンをじっと見つめている。
その眼差しは、病人のそれというより、獲物を狙うハンターのようだった。
僕は言われた通りにプッチンプリンを差し出した。
プラスチックのカップに入ったそれは、つるんとした表面が照明を反射して輝いている。
少年が弱々しい手でそれを受け取ろうとした、その瞬間だった。
「あの、お皿を…」。
僕の脳内では、「え、皿?
」という疑問符がぐるぐる回った。
病気で弱っているとはいえ、まさかこの状況で皿を要求してくるとは思わなかった。
てっきり、そのままスプーンで食べるものだと思っていたから、一瞬、自分の耳を疑った。
「お皿?
」と聞き返すと、少年は少し力を込めた声で、しかし掠れたままのトーンで言った。
「プッチン…するから」。
その言葉に、僕はようやく合点がいった。
ああ、なるほど。
「プッチン」は、このプリンの醍醐味であり、儀式なのだ。
底のつまみをパキッと折って、空気が入ることでプリンがプルンと皿の上に落ちる。
あの瞬間が、プッチンプリンを食べるときのハイライトなのだ。
皿の上に乗ったプリンの、あの完璧な円柱形と、皿に広がるカラメルソースのコントラスト。
あれこそが「完成形」であり、カップのままスプーンで食べるのは、いわば「未完成」なのだ。
僕自身、いつの間にかカップのまま食べるのが当たり前になっていたけれど、言われてみれば、確かに皿に出した方が「それっぽい」気がする。
急いでリビングに戻り、食器棚から一番平らな白い皿を選んだ。
そして、彼の部屋に戻って皿を差し出すと、少年はゆっくりとプリンのカップを逆さまにして、底のつまみを「パキッ」と折った。
その音は、病室に響くとは思えないほどクリアで、どこか神聖にすら聞こえた。
そして、プルンと皿の上に落ちたプリンは、見事なまでにその美しい姿を現した。
彼は満足げに、そしてかすかに微笑んだように見えた。
その時の彼の顔は、熱にうなされているにもかかわらず、どこか誇らしげだった。
まるで、長年受け継がれてきた秘伝の技を披露した職人のようだった。
僕も子どもの頃は、あの「プッチン」の瞬間を楽しみにしていたはずだ。
でも、いつの間にか大人になって、効率や手軽さを求めるようになって、あの小さな儀式を忘れてしまった。
コンビニで買ったお弁当をパックのまま食べるのが当たり前になり、インスタントコーヒーはマグカップに直接お湯を注ぐ。
食パンは袋から直接出して、立ったままかじることだってある。
そういえば、昔は目玉焼きを焼くにも、卵を割る前にフライパンを温める時間を計ったり、黄身を崩さないようにそっと落とす、とか、自分なりの手順があったような気もする。
今じゃ、火にかけてすぐ卵を割り入れて、半熟になったらサッと皿にスライドさせて終わりだ。
あの日の少年は、たとえ体が辛くても、あの小さな「儀式」を尊重した。
それはきっと、彼にとって、病気で失われた日常の小さな楽しみを取り戻す行為だったのかもしれない。
完璧なプリンの姿を視覚で楽しみ、底のつまみを折る音を聞き、そして、プルンとした食感を舌で味わう。
五感をフルに使って楽しむ、彼のささやかな抵抗だったのかもしれない。
僕らは大人になると、とかく効率を重視しがちだ。
でも、日々の暮らしの中にある、そんなささやかな「儀式」こそが、心を豊かにしてくれるものなのかもしれない。
淹れたてのコーヒーを、お気に入りのカップに注いでゆっくりと香りを味わう時間。
新しく買った本を開く前に、表紙を撫でて紙の匂いを嗅ぐ瞬間。
僕はあの少年から、忘れかけていた大切な何かを思い出させてもらった気がした。
皆さんも、日々の生活の中で、つい忘れがちな「プッチン」の儀式、大事にしているもの、ありませんか?
きっと、それが日常のちょっとしたスパイスになるはずだ。
ああ、それにしても、あの少年が皿に出したプッチンプリン、ものすごく美味しそうだったなあ。
僕も今度、ちゃんと皿に出して食べよう。
もちろん、一番平らな白い皿で。
💡 このエッセイは、Togetterの話題から着想を得て、2026年の視点で書かれた創作記事です。