📝 この記事のポイント
- 美容院の待ち時間、デジタル雑誌をめくりながら、ふとスマホの通知に気づいたのである。
- 画面に表示されたのは、AIが自動生成した今日のニュースダイジェスト。
- その中の一本が、私の意識の奥底に微かな波紋を広げた。
美容院の待ち時間、デジタル雑誌をめくりながら、ふとスマホの通知に気づいたのである。
画面に表示されたのは、AIが自動生成した今日のニュースダイジェスト。
その中の一本が、私の意識の奥底に微かな波紋を広げた。
――「工場での朝のラジオ体操、Z世代はなぜ馬鹿にするのか?
」という見出しであった。
私は2026年の都市で生きる29歳。
リモートワークが生活の中心を占め、身体を動かす機会といえば、フィットネスアプリの指示に従うか、推し活イベントで跳ね回る程度なのである。
工場という空間そのものが、私にとって既にノスタルジーの領域に片足を突っ込んでいる。
そこに「ラジオ体操」というさらに古風な行為が重なる時、確かに「ダサい」「無駄」という脊髄反射が起こるのも無理はないと、記事を読みながら漠然と感じたのである。
記事は、ラジオ体操を嘲笑するSNSの投稿を羅列していた。
AIが生成したミーム画像が、工場労働者の無表情な動きを揶揄している。
――「生産性ゼロ」「時間の無駄」「AIにやらせろ」といったコメントが並んでいた。
効率性とデータドリブンな思考に慣れ親しんだ現代人にとって、その行為は非合理的に映るのだろう。
しかし、私の内側には、この単純な嘲笑に対するある種の違和感が燻っていたのである。
なぜ、未だに多くの工場でラジオ体操は続けられているのだろうか。
AIが業務効率を極限まで高め、物理労働の多くがロボットに代替されつつあるこの時代に、人間が一斉に腕を振り、体を屈伸させる光景は、一見すると時代錯誤極まりない。
――その疑問は、私の探求心を静かに刺激したのである。
週末、私は昔からの友人で、現在も製造業の現場で働くアキラに連絡を取った。
彼とは大学時代からの付き合いで、工場勤務を選んだ彼は、リモートワークが主流の私の生活とは全く異なるリズムで生きている。
――彼もまた、Z世代の一員なのである。
ビデオ通話越しに、私は率直に問いかけた。
「なあアキラ、まだ工場でラジオ体操とかやってるの?
正直、意味ある?
」画面の向こうのアキラは、少しだけ苦笑いを浮かべた。
彼の顔には、油と金属の匂いが染み付いているかのような、都市の喧騒とは違う落ち着きがあったのである。
「ああ、やってるよ。毎日な」彼は淡々と答えた。――「労災対策のため、ってのが建前だけどな。それだけじゃない」その言葉に、私は耳を傾けたのである。
アキラは続けた。
「確かに最初は俺も馬鹿にしてた。
真面目にやるのが恥ずかしい、ってな。
先輩たちもなんだかんだ言いながらやってるのを見て、形式的なもんだと思ってた」彼の声は、どこか遠い記憶を探るように響いたのである。
彼は工場で働き始めて一年が経った頃の体験を語り始めた。
ある日、彼は重い部品を運ぶ作業中に、不注意から腰を捻ってしまったという。
幸い大事には至らなかったものの、その瞬間の痛みが今でも忘れられないと彼は言った。
――その日、彼は体操をサボっていたのである。
「その日から、俺は真面目にやるようになった」アキラは言った。
「嘘みたいに聞こえるかもしれないけど、ちゃんと体操した日は、身体の動きが違うんだ。
可動域が広がる、っていうか。
ちょっとした段差につまずくことも減ったし、重いものを持つ時も、変な力が入らなくなった」彼の言葉には、経験に裏打ちされた確かな実感が込められていたのである。
彼の話を聞きながら、私はリモートワーク中の自分の体を思い出した。
一日中ディスプレイに向かい、猫背になり、肩は凝り固まっている。
急に立ち上がると、膝が軋むような感覚を覚えることもある。
――身体は、思ったよりも正直なのである。
だが、アキラの言葉は単なる身体的効果に留まらなかった。
彼はさらに深い本質を語り始めた。
「でもな、もっと大事なことがあるんだ」彼の表情は、真剣さを増していた。
「朝、みんなで一斉に身体を動かす。
同じリズムで、同じ方向を向いて。
彼は続けた。
「最初はバラバラだったのが、体操が終わる頃には、なんとなく一体感が生まれてる。
その日の作業が始まる前に、全員で呼吸を合わせるみたいな感覚、と言えばいいかな」――「AIがどんなに進化しても、ロボットがどんなに精密になっても、人間の身体と身体が共鳴し合う感覚は、代替できないんだ」彼の言葉は、私の心に深く響いたのである。
私はハッとした。
SNSで飛び交う「無駄」「非効率」という言葉の裏には、人間が人間として生きる上で不可欠な、ある種の「呪術」が隠されていたのではないか、と。
ラジオ体操は、単なるストレッチではない。
それは、集団の身体を調律し、精神を集中させ、連帯の呪力を高めるための儀式なのである。
AIが全ての最適解を提示する現代において、私たちは「非効率」に見えるものの中にこそ、人間性そのものの本質が潜んでいることを見落としがちなのである。
物価高騰の中、節約志向が高まり、あらゆる無駄を排除しようとする一方で、私たちは身体を動かす「非効率」な習慣を捨て去ろうとしている。
――しかし、それは本当に無駄なのだろうか。
アキラは続けた。
「俺たちの工場では、ベテランも若手も、ラジオ体操の時は同じ動きをする。
普段は寡黙な職人さんも、体操の時だけはちょっと笑顔を見せたりするんだ」――「言葉を交わさなくても、身体で通じ合える。
それが、俺たちのチームワークの基盤になってる」彼の声は、淡々としていながらも、確かな温かさを帯びていたのである。
リモートワークが定着し、ハイブリッドワークが日常となった私たちの生活では、物理的な接触が極端に減った。
チームメイトの顔を見るのはディスプレイ越し、声を聞くのはチャットアプリ経由。
――その結果、私たちは知らず知らずのうちに、身体的な連帯感を失っていたのではないか。
SNS疲れや情報過多への反動で、私たちは「エモ消費」や「推し活」に走る。
それは、失われた人間的な繋がりや感動を求める本能的な行動なのである。
しかし、その「エモさ」は、往々にしてデジタル空間の中に閉じ込められている。
――リアルな身体性からくる連帯感は、その先にこそ存在するのではないか。
美容院でのカットが終わり、私は席を立った。鏡に映る自分は、先ほどまでとは少し違って見えた。――アキラの話は、私の世界観を静かに転換させたのである。
私は、私たちの社会が効率性の名の下に切り捨てようとしている「非効率」なものの中にこそ、人間が本来持つべき「呪術」のような力が宿っていることに気づかされた。
ラジオ体操は、その最もプリミティブな形の一つなのである。
身体を動かすこと。
皆で同じリズムを刻むこと。
それは、単なる健康増進のためだけではない。
それは、個々の身体を調整し、集団の意識を一つに統合する、原始的で強力な「術式」なのである。
――労災対策という合理的な理由を超えて、そこには人間が人間として生き、共に働くための根源的な意味が込められていたのである。
AIが私たちの生活を劇的に変える2026年。
私たちは、失われつつある身体性、そしてそれを通じて生まれる連帯感の価値を再認識する時期に来ているのかもしれない。
――工場でのラジオ体操は、その無意識の抵抗であり、人間にしか生み出せない「呪力」の源泉なのである。
私は美容院を出て、街の雑踏に紛れ込んだ。
ふと、大きく伸びをして腕を回してみた。
肩の周りのこわばりが、少しだけ緩んだような気がした。
――その小さな身体の感覚が、私にとって、今日手に入れた最も確かな「呪術」だったのである。
💡 このエッセイは、Togetterの話題から着想を得て、2026年の視点で書かれた創作記事です。
📚 あわせて読みたい








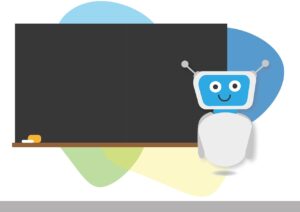


コメント