📝 この記事のポイント
- 2026年1月22日、東京の朝はいつも通り、いや、いつも以上にせわしない空気を孕んでいた。
- オリンピックの熱狂が冷め、AI技術の進化が加速する中、社会は目まぐるしく変化し続けている。
- 満員電車の窓に映る自分の顔は、そんな時代の波に飲まれまいと必死に食らいつく、疲れ切ったサラリーマンそのものだった。
2026年1月22日、東京の朝はいつも通り、いや、いつも以上にせわしない空気を孕んでいた。オリンピックの熱狂が冷め、AI技術の進化が加速する中、社会は目まぐるしく変化し続けている。満員電車の窓に映る自分の顔は、そんな時代の波に飲まれまいと必死に食らいつく、疲れ切ったサラリーマンそのものだった。
毎日同じ時間に家を出て、同じ電車に乗り、同じようにスマホを弄る人々。まるでプログラムされたかのような日常に、時折、無性に息苦しさを感じることがある。今日の僕は、その「時折」が訪れた日だった。
会社に着き、いつものようにコーヒーを淹れ、パソコンを立ち上げる。画面に映る無機質な数字の羅列と、上司からの容赦ない指示。まるでベルトコンベアに乗せられた部品のように、ただひたすら作業をこなしていく。そんな日々の中で、ふと、自分の存在意義を見失ってしまうことがある。
昼食は、会社の近くにある小さなカフェで摂ることにした。窓際の席に座り、サンドイッチとコーヒーを注文する。店内に流れる穏やかなジャズの音色が、少しだけ心を落ち着かせてくれる。
隣の席には、若い女性が一人で座っていた。彼女は、ノートパソコンに向かって何かを打ち込んでいる。時折、眉をひそめたり、微笑んだりしながら、真剣な表情で画面を見つめている。彼女の姿を見ていると、なんだか無性に羨ましくなった。彼女は、自分のやりたいことを見つけて、それに向かって努力しているのだろうか。それとも、僕と同じように、日々の仕事に追われているだけなのだろうか。
ふと、テーブルの上に置かれた彼女のマグカップに目が留まった。マグカップには、手作りのクッキーが数枚添えられている。そのクッキーを見て、僕はなぜか、子供の頃の記憶が蘇ってきた。
小学生の頃、母がよく手作りのクッキーを焼いてくれた。焼き立てのクッキーは、ほんのり温かく、甘くて優しい味がした。僕は、そのクッキーを食べるのが大好きだった。母は、僕が喜ぶ顔を見るのが嬉しかったのだろう。いつも、たくさん焼いてくれた。
あの頃の僕は、将来のことなど何も考えていなかった。ただ、目の前の楽しいことだけに夢中になっていた。友達と遊んだり、ゲームをしたり、漫画を読んだり。毎日が、刺激的でワクワクすることばかりだった。
しかし、大人になるにつれて、そんな気持ちは薄れていった。社会に出ると、責任や義務が重くのしかかってくる。自分のやりたいことよりも、やらなければならないことを優先しなければならない。気がつけば、僕は、子供の頃に夢見ていた自分とは、全く違う人間になっていた。
サンドイッチを食べ終え、カフェを出る。外は、まだ寒かった。街を歩きながら、僕は、あの若い女性のことを考えていた。彼女は、なぜ、あんなに真剣な表情でパソコンに向かっていたのだろうか。彼女は、自分の夢を追いかけているのだろうか。
その時、ふと、僕は、自分の部屋に眠っているギターのことを思い出した。大学生の頃、バンドを組んで音楽活動をしていた時期があった。ギターを弾くのが楽しくて、毎日、練習に明け暮れていた。しかし、就職を機に、ギターを弾く時間はなくなってしまった。ギターは、埃をかぶったまま、部屋の隅に置かれている。
会社に戻り、仕事に取り掛かる。しかし、どうしても、ギターのことが頭から離れない。夕方、僕は、思い切って、上司に早退を願い出た。上司は、少し驚いた顔をしたが、何も言わずに許可してくれた。
家に帰り、部屋の隅に置かれたギターを取り出す。ギターは、長い間放置されていたため、埃まみれになっていた。僕は、丁寧にギターを拭き、弦を張り替えた。そして、久しぶりにギターを弾いてみた。
指は、思うように動かない。音も、以前のように綺麗に出ない。それでも、僕は、ギターを弾き続けた。気がつけば、時間は、あっという間に過ぎていた。
夕食の時間になった。冷蔵庫を開けると、中には、作り置きのカレーがたっぷり入っていた。週末に、時間を持て余して、大量に作ったものだ。冷蔵庫を開けた瞬間、ふわりとカレーのスパイシーな香りが漂ってきた。
「そういえば、明日はカレーにしようと思ってたんだ」
僕は、鍋にカレーを移し、温め始めた。グツグツと煮えるカレーを見ていると、なぜか、心が温かくなるような気がした。別に特別なカレーではない。スーパーで買ったルーを使った、ごく普通のカレーだ。それでも、僕にとっては、特別な意味を持つカレーだった。
それは、僕が、自分のために作ったカレーだからだ。誰かに言われたわけでもなく、義務感から作ったわけでもない。ただ、自分が食べたいと思って、作ったカレーなのだ。
カレーを食べる。口の中に広がるスパイシーな風味と、野菜の甘みが、疲れた体を癒してくれる。僕は、無我夢中でカレーをかき込んだ。
食べ終わると、なんだか、力が湧いてくるような気がした。明日も、頑張って生きていこう。そう思えるようになった。
カレーを作りすぎたなぁ、とぼんやり思った。明日も明後日も、カレーだ。でも、悪くない。むしろ、良い。なぜなら、僕は、明日も生きる気満々だからだ。
SNSを開くと、タイムラインには、友人たちの楽しそうな投稿が並んでいる。旅行の写真、美味しい料理の写真、恋人とのツーショット写真。それらを見ていると、少しだけ、心がざわつく。
「みんな、楽しそうだな」
僕は、そう呟いた。自分だけが、取り残されているような気がした。
しかし、すぐに、その感情は消え去った。僕は、自分の作ったカレーを、誇らしく思った。たとえ、誰かに見せるわけでもなくても、自分のために作ったカレーは、かけがえのないものだ。
僕は、スマホを取り出し、カレーの写真を撮った。そして、SNSに投稿した。
「自分で作った鍋いっぱいのカレー。明日も生きる気マンマンでワロタ」
短い文章とともに、カレーの写真をアップロードした。
すぐに、友人たちからコメントが届いた。
「美味しそう!」「元気そうでよかった!」「カレー食べたい!」
僕は、一つ一つ丁寧に返信した。
その時、ふと、気がついた。僕は、決して一人ではない。たくさんの友人たちが、僕を支えてくれている。そして、僕は、自分の作ったカレーを通して、彼らと繋がっているのだ。
夜、眠りにつく前に、僕は、ギターを抱きしめた。明日から、また、少しずつ、ギターを弾いてみよう。そう思った。
2026年1月23日。僕は、昨日よりも少しだけ、希望に満ちた気持ちで目覚めた。
冷蔵庫を開けると、そこには、まだたくさんのカレーが残っていた。琥珀色に輝くカレーは、まるで希望の光のようだった。
電車に乗り、会社に向かう。窓に映る自分の顔は、昨日よりも少しだけ、明るくなっていた。
現代社会は、常に変化し続けている。その変化のスピードに追いつくのは、容易ではない。しかし、それでも、僕たちは、生きていかなければならない。
そんな時代を生き抜くために、僕たちに必要なのは、大きな夢や目標ではなく、日々の小さな積み重ねなのかもしれない。
例えば、美味しいコーヒーを淹れること。
例えば、好きな音楽を聴くこと。
例えば、手作りのカレーを食べること。
そうした小さなことの積み重ねが、僕たちの心を癒し、明日への活力となるのだ。
そして、何よりも大切なのは、自分自身を大切にすることだ。自分の好きなことを見つけ、それを大切にすること。自分の心を大切にし、無理をしないこと。
そうすることで、僕たちは、どんな困難にも立ち向かうことができる。
琥珀色のカレーは、僕に、そんなことを教えてくれた。
明日も、明後日も、その先も、僕は、カレーを作り続けるだろう。そして、そのカレーを通して、たくさんの人々と繋がり、共に生きていくのだ。
それは、ささやかだけれど、確かな希望の光だ。
※このエッセイは、Togetterのまとめから着想を得て創作されたフィクションです。
📚 あわせて読みたい







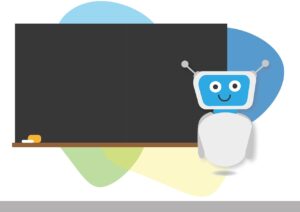



コメント