📝 この記事のポイント
- 2026年1月20日、東京は珍しく雪だった。
- 朝から降り続いた雪は、アスファルトの上でシャーベット状になり、歩くたびにキュッキュッと音を立てる。
- 僕は丸の内にあるオフィスビルのカフェで、熱いコーヒーをすすりながら、ぼんやりと窓の外を眺めていた。
2026年1月20日、東京は珍しく雪だった。朝から降り続いた雪は、アスファルトの上でシャーベット状になり、歩くたびにキュッキュッと音を立てる。僕は丸の内にあるオフィスビルのカフェで、熱いコーヒーをすすりながら、ぼんやりと窓の外を眺めていた。
今日は、AI倫理に関する社内研修がある。僕のようなシステムエンジニアにとって、AIの倫理は避けて通れない問題だ。しかし、正直なところ、僕はまだピンときていない。AIが進化し、社会に浸透していくことは理解できる。でも、それが具体的に僕たちの生活や感情にどう影響するのか、想像力が追いつかないのだ。
「遅れてごめん!」
突然、背後から明るい声が聞こえた。振り返ると、大学時代の友人であるユキが、息を切らせて立っていた。ユキは、フリーランスのデザイナーとして活躍している。クリエイティブな才能にあふれ、常に新しいものにアンテナを張っている彼女は、僕とは対照的な存在だ。
「大丈夫だよ。僕も今来たところ」
僕はそう言って、ユキの向かい側の席を勧めた。ユキはコートを脱ぎ、深呼吸をしてから言った。
「聞いてよ!さっき、すごい店見つけたの!」
「すごい店?」
「そう!角煮定食がめちゃくちゃ美味しい店!しかも、ご飯を大盛りにしたら、ありえないくらい盛られて出てきたのよ!まるでAIが作ったんじゃないかってくらい完璧な山盛りで!」
ユキは興奮気味に、その店の角煮定食について語り始めた。僕の頭の中には、マンガに出てくるような、巨大なご飯の山と、テカテカと輝く角煮が浮かんだ。
「で、結局、完食したの?」
僕は思わず聞いてしまった。ユキはニヤリと笑って言った。
「もちろん!美味しいものは残せない主義なの!」
その言葉を聞いて、僕は少しだけ心が軽くなった。AIの倫理とか、難しい問題は一旦置いておいて、目の前の美味しいものを楽しむ。それが、今の僕に必要なことなのかもしれない。
「夜、その店行ってみない?」
僕はユキに提案した。ユキは目を輝かせて言った。
「行く!絶対行く!」
研修が終わった後、僕たちは約束通り、ユキが見つけた角煮の店に向かった。店は、オフィス街から少し離れた、ひっそりとした場所に佇んでいた。店内は、木の温もりを感じさせる落ち着いた雰囲気で、カウンター席とテーブル席がいくつか並んでいる。
僕たちはカウンター席に座り、迷わず角煮定食を注文した。ユキはもちろん、ご飯大盛りだ。しばらくして、運ばれてきた角煮定食を見て、僕は言葉を失った。ユキが言っていた通り、ご飯は本当にマンガみたいな山盛りだった。角煮も、信じられないくらい大きい。
「すごい…」
僕は思わずつぶやいた。ユキは、まるで自分のことのように誇らしげに言った。
「でしょ?この店、絶対流行ると思うんだ!」
僕たちは、黙々と角煮定食を食べ始めた。角煮は、とろけるように柔らかく、口の中で甘辛い味が広がる。ご飯も、ふっくらと炊き上げられていて、角煮との相性が抜群だ。
しかし、食べ進めていくうちに、僕は少し違和感を覚えた。確かに、角煮もご飯も美味しい。でも、どこか計算されているような、完璧すぎる味がするのだ。まるで、AIが分析した最適なレシピに基づいて作られたような。
「ねえ、ユキ。この角煮、美味しくない?」
僕はユキに聞いてみた。ユキは、箸を止めて、少し考え込んでから言った。
「美味しいよ。でも、確かに、ちょっと完璧すぎるかも。なんか、人間味が足りないっていうか…」
ユキも、僕と同じように感じていたようだ。僕たちは、顔を見合わせて苦笑いした。
「もしかして、この店の店主って、AIなの?」
ユキが冗談めかして言った。僕は、ありえないと思いながらも、少しだけ心がざわついた。
その夜、家に帰ってからも、角煮の味が頭から離れなかった。僕は、インターネットでAIと料理に関する記事を検索してみた。すると、AIがレシピを開発したり、料理の味を分析したりする技術は、すでに実用化されていることがわかった。
AIは、膨大なデータを分析し、人間の味覚を数値化することができる。そして、最も美味しい組み合わせを導き出すことができるのだ。つまり、AIが作った料理は、理論上、完璧な味になるはずだ。
しかし、完璧な味が、本当に美味しいのだろうか?僕は、疑問に思った。料理は、単なる栄養補給の手段ではない。そこには、作り手の想いや、歴史、文化、そして、何よりも「人間味」が込められているはずだ。
僕の祖母は、料理が上手だった。祖母の作る料理は、いつもどこか懐かしい味がした。それは、祖母が長年培ってきた経験と、家族への愛情が込められているからだろう。祖母の料理は、決して完璧な味ではなかった。でも、僕にとっては、世界で一番美味しい料理だった。
AIが作った料理には、愛情や思い出は込められていない。そこにあるのは、あくまでもデータに基づいた計算された美味しさだけだ。僕は、そんな料理を本当に美味しいと感じることができるのだろうか?
僕は、ふと、自分が開発しているAIシステムについて考え始めた。僕たちは、より効率的で、より正確なAIシステムを開発しようとしている。しかし、その過程で、何か大切なものを置き去りにしていないだろうか?
AIは、人間の仕事を奪うかもしれない。AIは、人間の感情を理解できないかもしれない。AIは、人間の創造性を阻害するかもしれない。そんな未来が、本当に僕たちが望んでいる未来なのだろうか?
僕は、AIの可能性を信じている。AIは、私たちの生活を豊かにし、社会をより良くすることができる。しかし、そのためには、AIの倫理について、もっと深く考える必要がある。AIは、あくまでも道具だ。それをどう使うかは、私たち人間次第なのだから。
2026年1月21日、僕は、AI倫理に関する社内研修に参加した。研修の内容は、予想していたよりもずっと具体的で、実践的なものだった。様々な事例を通して、AIが社会に与える影響や、倫理的な課題について深く学ぶことができた。
研修の最後に、講師の先生が言った。
「AIは、私たちの未来を大きく変える力を持っています。しかし、AIがもたらす未来は、私たち自身の手で形作っていく必要があります。AIと人間が共存し、より良い社会を築くために、私たち一人ひとりが、AIの倫理について真剣に考え、行動していくことが大切です。」
その言葉を聞いて、僕は、角煮の店のことを思い出した。完璧な味の角煮は、私たちに、AIと人間の関係について考えるきっかけを与えてくれた。AIは、私たちの生活を便利にするかもしれない。しかし、人間らしさや温かさを忘れずに、AIと向き合っていくことが大切だ。
研修の後、僕はユキに連絡した。
「今度、祖母の家に行ってみない?祖母の料理、きっとユキも好きになると思うよ。」
ユキは、少し驚いた様子で言った。
「え、いいの?おばあちゃんの料理、ぜひ食べてみたいな。」
僕は、ユキの声に安堵した。AIの時代だからこそ、人間の温もりや愛情を大切にしたい。そして、それを、大切な人たちと分かち合いたい。
2026年1月22日、僕は、ユキと一緒に、祖母の家に向かった。雪は止み、空は晴れ渡っていた。太陽の光が、雪景色をキラキラと輝かせている。僕は、未来への希望を胸に、一歩ずつ歩き出した。
—
キーワード: AI倫理、角煮、ご飯大盛り、人間味、愛情、テクノロジー、未来、社会、共存、研修、雪、東京、カフェ、友人、デザイナー、完璧な味、手作り、祖母、料理、可能性、希望、温もり、SNS世代、2026年、食、感情、デジタル、アナログ、バランス、価値観、葛藤、選択、日常、変化、成長。
※このエッセイは、Togetterのまとめから着想を得て創作されたフィクションです。
📚 あわせて読みたい








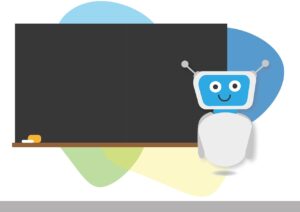


コメント