📝 この記事のポイント
- 僕はいつものように、満員電車の網棚を見上げていた。
- 吊り革につかまる腕の角度が、微妙に隣の人と干渉しないように、神経を尖らせている。
- スマホのニュースアプリを開くと、トップ記事は予想通り、生成AIに関するものだった。
2026年1月20日。僕はいつものように、満員電車の網棚を見上げていた。吊り革につかまる腕の角度が、微妙に隣の人と干渉しないように、神経を尖らせている。スマホのニュースアプリを開くと、トップ記事は予想通り、生成AIに関するものだった。
「…またか」
小さく呟いた。最近、生成AI関連のニュースを見ない日はない。今日の記事の見出しは、「誤字脱字、新たなコミュニケーション戦略として台頭か」。
…やっぱり、そうなるよな、と僕は思った。
事の発端は、数ヶ月前のこと。僕が担当するプロジェクトで、生成AIを駆使した提案資料を作成した時のことだった。完璧なロジック、洗練されたデザイン、淀みない文章。自信満々で上司に提出したところ、返ってきたのは意外な言葉だった。
「…なんか、AIっぽいね」
AIっぽい? それが褒め言葉じゃないことは、すぐに理解できた。上司は続けた。
「人間味がないっていうか。完璧すぎるんだよ。もっと、こう…粗さというか、温かみが欲しいんだよね」
温かみ、か。AIに温かみを求めるなんて、まるでSF映画のワンシーンみたいだ。でも、上司の言いたいことは分かった。完璧な文章は、どこか冷たく、無機質に感じられる。まるで、心がない機械が書いた文章のようだ。
その日から、僕は意識的に資料に「誤字」を混ぜるようになった。句読点の位置を微妙に変えたり、漢字をひらがなで書いたり、意図的に変換ミスを残したり。まるで、小学生が書いた作文のような、稚拙な文章を目指した。
最初は抵抗があった。完璧主義な僕にとって、誤字は許せないものだったからだ。でも、効果はすぐに現れた。資料を見た上司は、満足げに頷いた。
「うん、これなら人間が書いたって分かるよ」
複雑な気持ちになった。完璧な文章はAIっぽいと言われ、不完全な文章は人間らしいと言われる。一体、僕は何を目指しているんだろう?
カフェに移動して、ノートパソコンを開いた。目の前のディスプレイには、完成したばかりの企画書が映し出されている。完璧なロジック、美しいレイアウト、そして…意図的に残された、いくつかの誤字。
「…本当に、これでいいのかな」
隣の席では、若い女性がイヤホンをしながら、一心不乱にスマホをタップしている。彼女もまた、僕と同じように、生成AIと向き合っているのかもしれない。
ふと、大学時代の友人の顔が浮かんだ。彼は、卒業後すぐにAI関連のベンチャー企業に就職し、最先端の技術開発に携わっている。ある日、彼と飲んだ時、彼はこう言った。
「AIは、あくまでツールだよ。人間がどう使うかが問題なんだ」
彼の言葉を思い出す。AIは、人間の仕事を奪う存在ではない。人間の創造性を拡張する、強力なツールなのだ。しかし、そのツールを使いこなすためには、人間自身も変わらなければならない。
誤字を残すことは、本当に人間らしさの証明になるのだろうか? それは、まるで原始的なチューリングテストのようだ。機械に人間だと認識させるために、わざと欠陥を装う。
でも、本当に大切なのは、欠陥を装うことではなく、自分の言葉で、自分の感情を伝えることではないだろうか。
僕は、企画書から誤字を全て削除した。そして、代わりに、自分の言葉で、プロジェクトへの熱意を書き加えた。
「このプロジェクトは、単なるビジネスではありません。私たちが目指すのは、〇〇という価値を、社会に提供することです。そのために、私は…」
自分の言葉で書くことは、想像以上に難しかった。AIのように完璧な文章は書けない。でも、そこに込められた熱意は、AIには決して真似できないものだ。
送信ボタンを押す。少しだけ、不安と期待が入り混じった。
数時間後、上司から返信が来た。
「見たよ。前のより、ずっと良くなったね。熱意が伝わってきたよ」
その言葉に、僕は心から安堵した。
電車の中で、僕は再びニュースアプリを開いた。今度は、生成AIの倫理に関する記事だった。
「…結局、AIとどう向き合うかってことなんだよな」
独り言を呟いた。
誤字を残すことは、一時的な対策にしかならない。本当に必要なのは、AIに負けない、人間の価値を創造することだ。それは、創造性かもしれないし、共感力かもしれないし、人間ならではの感情かもしれない。
2026年。生成AIは、私たちの生活に深く浸透している。それは、便利な道具であると同時に、私たちに新たな問いを投げかけている。
人間とは何か? 何が人間らしさなのか?
その答えは、きっと、AIとの共存の中で、少しずつ見えてくるのだろう。
僕は、電車を降りて、オフィスに向かった。今日の夕焼けは、いつもより少しだけ、鮮やかに見えた。
そして、僕は確信した。
誤字は、レガシーではない。それは、私たちが過去から受け継ぎ、未来へと繋げていく、人間らしさの探求の始まりなのだ。
※このエッセイは、Togetterのまとめから着想を得て創作されたフィクションです。
📚 あわせて読みたい








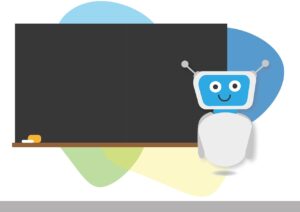


コメント