📝 この記事のポイント
- 2026年1月19日、都心の電車は今日も満員だった。
- 押しつぶされたアクリル板の向こうに、ぼんやりと広告が浮かんでいる。
- その無機質な輝きが、目の前の現実とのギャップを際立たせる。
2026年1月19日、都心の電車は今日も満員だった。押しつぶされたアクリル板の向こうに、ぼんやりと広告が浮かんでいる。AI搭載スマート冷蔵庫の宣伝。その無機質な輝きが、目の前の現実とのギャップを際立たせる。僕は、スマホを握りしめ、ニュースアプリをスクロールしていた。
今日は、新しいプロジェクトのキックオフミーティング。広告代理店に入って3年目、ようやく少し責任のある仕事を任されるようになった。胸の高鳴りと同時に、言いようのない不安が押し寄せる。このプロジェクトが成功するかどうかだけでなく、自分がこの仕事に向いているのかどうか、そもそも自分は何がしたいのか、そんな根本的な問いが頭の中をぐるぐると回る。
ふと、目に留まったのは、地方創生をテーマにしたドキュメンタリー番組の記事。過疎化が進む村に、若い世代が移住し、新たなコミュニティを築こうとする姿を追ったものだった。記事を読み進めるうちに、画面越しにも関わらず、彼らの熱意と、その裏にある葛藤がひしひしと伝わってきた。
(一体、彼らを突き動かしているものは何なんだろう?)
僕自身、東京で生まれ育ち、特に不自由のない生活を送ってきた。しかし、心の奥底には、常に何か満たされないものがある。それは、モノや情報に溢れた現代社会の中で、自分が本当に大切にしたいものが見つからない、そんな焦燥感なのかもしれない。
電車が駅に着き、僕は人波に押し出されるようにホームへ降り立った。オフィス街の喧騒が、さっきまで感じていた静かな感動をかき消していく。駅前のカフェに立ち寄り、アイスコーヒーを注文した。ミーティングまでの短い時間、少しでも心を落ち着かせたかった。
カフェの窓際の席に座り、僕は再びスマホを取り出した。SNSを開くと、友人たちの華やかな投稿が目に飛び込んでくる。海外旅行、高級レストラン、最新ガジェット…。きらびやかな日常が、まるで万華鏡のように映し出される。
(みんな、楽しそうだなぁ…)
僕は、心の中で小さく呟いた。もちろん、SNSに投稿されるのは、ほんの一部分でしかないことは分かっている。それでも、どうしても他人と比べてしまう自分がいる。
「あ、すみません、これどうぞ。」
突然、背後から声が聞こえた。振り返ると、年配の女性が立っていた。彼女は、僕のテーブルに、小さな包みをそっと置いた。
「これ、落とされたみたいで。」
僕は、慌てて自分のカバンを確認した。確かに、中身が少し飛び出している。
「ありがとうございます!助かります。」
僕は、深く頭を下げた。女性は、にこやかに微笑み、立ち去って行った。
包みを開けてみると、中には古い写真が入っていた。白黒写真の人物は、見覚えのない祖父母だろうか。いつの時代のものだろうか。端が少し破れていたり、色褪せていたりするが、丁寧に保管されていたことがわかる。
写真を見ているうちに、ふと、幼い頃の記憶が蘇ってきた。祖母の家で、古いアルバムを一緒に見た時のこと。祖母は、一枚一枚の写真について、楽しそうに語ってくれた。その時の、温かい光に包まれたような感覚が、鮮明に蘇ってきた。
(写真って、時間が封じ込められているんだな…)
僕は、改めて写真を見つめた。写真に写っている人々は、今、どこで何をしているのだろうか。彼らも、僕と同じように、悩み、苦しみ、そして喜びを感じて生きてきたのだろうか。
ミーティングの時間になったので、僕はカフェを出て、オフィスに向かった。エレベーターの中で、僕は再びスマホを取り出した。SNSを開くと、さっきまで感じていた焦燥感は、少しだけ和らいでいた。
(そうだ、自分には、自分だけの時間があるんだ。)
僕は、そう思った。他人と比べるのではなく、自分のペースで、自分のやりたいことを見つけていけばいい。焦らず、ゆっくりと、自分の時間を修繕していくように。
キックオフミーティングは、予想以上にスムーズに進んだ。新しいプロジェクトのメンバーは、皆、個性豊かで、熱意に満ち溢れていた。僕は、彼らと一緒に仕事ができることに、喜びを感じた。
ミーティングが終わった後、僕は、カフェで拾った写真を、会社の休憩室の掲示板に貼った。写真の下には、「落とし物です。お心当たりのある方は、ご連絡ください。」と書いたメモを添えた。
数日後、掲示板の写真を見たという女性から、連絡があった。彼女は、写真に写っている人物の孫娘だった。彼女は、幼い頃に両親を亡くし、祖父母に育てられたという。写真は、祖父母が若い頃に撮影されたもので、彼女にとって、とても大切なものだった。
「本当に、ありがとうございます。まさか、見つかるとは思っていませんでした。」
電話口の彼女の声は、震えていた。僕は、彼女に、写真をカフェで拾った時のことを話した。彼女は、何度も感謝の言葉を口にした。
後日、彼女は、お礼にと、手作りのクッキーを会社に持ってきてくれた。クッキーは、とても美味しかった。僕は、彼女と、祖父母のことや、幼い頃の思い出について、話をした。
彼女との出会いは、僕にとって、大きな転機となった。彼女との会話を通して、僕は、自分が本当に大切にしたいものに気づいた。それは、人との繋がり、温かい心の交流、そして、未来に繋がる小さな希望だった。
それからというもの、僕は、仕事に対する姿勢が変わった。ただ目の前の仕事をこなすのではなく、その仕事を通して、誰かの役に立ちたい、誰かを笑顔にしたい、そう思うようになった。
もちろん、全てが順風満帆に進んだわけではない。壁にぶつかることもあったし、失敗することもあった。それでも、僕は、諦めずに、自分のペースで、自分のやりたいことに挑戦し続けた。
数年後、僕は、独立し、自分の会社を立ち上げた。会社では、地方創生をテーマにしたプロジェクトを多く手がけた。過疎化が進む村に、若い世代が移住し、新たなコミュニティを築くための支援を行った。
ある日、僕は、以前ドキュメンタリー番組で見た村を訪れた。村の人々は、皆、笑顔で迎えてくれた。彼らは、僕に、自分たちの手で育てた野菜や、手作りの工芸品をプレゼントしてくれた。
村の人々との交流を通して、僕は、自分が本当に求めていたものが、ここにあることを確信した。それは、モノや情報に溢れた都会では決して手に入れることのできない、温かい心の繋がりだった。
僕は、村の小学校で、子供たちに、自分の仕事について話をした。子供たちは、目を輝かせながら、僕の話に耳を傾けてくれた。
「僕たちは、みんなが笑顔で暮らせる、そんな未来を作りたいと思っています。」
僕は、子供たちに、そう語りかけた。子供たちは、大きな拍手で応えてくれた。
その夜、僕は、村の温泉に入り、星空を見上げた。満天の星空が、まるで宝石のように輝いていた。僕は、深呼吸をして、澄んだ空気を胸いっぱいに吸い込んだ。
(ああ、これが、僕の探し求めていたものなんだ。)
僕は、そう思った。僕は、自分の時間を修繕し、未来へと繋がる道を見つけた。
そして、2026年1月19日のあの日の出来事が、今の自分に繋がっているのだと、改めて実感した。あの時、カフェで拾った写真は、僕にとって、単なる落とし物ではなく、人生の道しるべだったのかもしれない。
僕は、これからも、自分のペースで、自分のやりたいことに挑戦し続けたい。そして、未来に向かって、一歩ずつ、歩んでいきたい。
※このエッセイは、Togetterのまとめから着想を得て創作されたフィクションです。
📚 あわせて読みたい







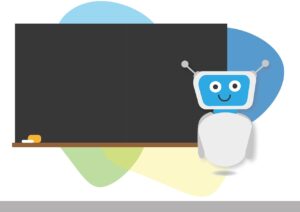



コメント