📝 この記事のポイント
- 都心のカフェは、週末の午後にも関わらず、仕事を持ち込む人々で賑わっていた。
- 僕は窓際の席で、熱いカフェラテをすすりながら、ぼんやりとスマホのニュースフィードを眺めていた。
- 目に飛び込んできたのは、「AIによる完全自動運転タクシー、都内で試験運行開始」という見出し。
2026年1月18日。都心のカフェは、週末の午後にも関わらず、仕事を持ち込む人々で賑わっていた。僕は窓際の席で、熱いカフェラテをすすりながら、ぼんやりとスマホのニュースフィードを眺めていた。目に飛び込んできたのは、「AIによる完全自動運転タクシー、都内で試験運行開始」という見出し。
(導入)
思わず苦笑してしまう。数年前まで、SFの世界の話だと思っていたことが、もうすぐそこまで来ているのだ。僕の仕事は、中小企業の広報戦略コンサルタント。時代の変化に対応しながら、クライアントの魅力を最大限に引き出すのが使命だ。しかし、AIの進化を目の当たりにすると、自分の仕事もいつかAIに取って代わられるのではないか、という不安が頭をもたげる。
隣の席では、若い女性が熱心にパソコンに向かっている。おそらく、僕と同じように仕事をしているのだろう。彼女の表情は真剣そのもので、画面に映る数字やグラフを食い入るように見つめている。ふと、彼女の肩越しに画面が目に入った。そこには、複雑な数式と、専門用語が羅列されていた。彼女の仕事は、僕には全く理解できない。
僕は、広報という仕事を選んだ理由を思い返していた。子供の頃から、文章を書くこと、人に何かを伝えることが好きだった。大学時代には、演劇サークルに所属し、脚本や演出を手がけていた。自分の言葉で人を感動させたり、笑わせたりすることに、何よりも喜びを感じていたのだ。
(展開)
しかし、社会に出ると、自分の理想と現実のギャップに直面する。クライアントの意向を汲みながら、売上を伸ばすための広報戦略を立てることは、必ずしも自分の理想とする表現とは限らない。時には、嘘ではないけれど、真実を少しだけ歪める必要もある。
そんな時、僕はいつも葛藤する。自分の仕事は、本当に社会の役に立っているのだろうか?誰かを幸せにしているのだろうか?もしかしたら、ただ企業の利益を追求するだけの、無意味な仕事なのではないか?
そんなことを考えていると、ふと、数日前に読んだニュース記事が頭をよぎった。「岩手県には麻酔吹き矢でクマを捕獲できる使い手は一人しかおらず後継者を養成することになったが常人には可能なのか?『園長が強すぎる…』」。
最初は、その記事を読んで、単純に面白いと思った。麻酔吹き矢でクマを捕獲するなんて、まるで時代劇の世界だ。しかし、よく考えてみると、それは決して笑い話ではない。クマは人里に現れ、人々の生活を脅かす存在だ。麻酔吹き矢でクマを捕獲することは、人々の安全を守るために、必要不可欠な技術なのだ。
そして、その技術を受け継ぐ人が、たった一人しかいないという事実に、僕は衝撃を受けた。その園長と呼ばれる人は、一体どんな人なのだろう?一体どんな思いで、クマと向き合っているのだろう?
僕は、その園長に、無性に会ってみたくなった。自分の仕事に迷い、将来に不安を感じている僕にとって、彼は何かヒントを与えてくれるのではないか、と思ったのだ。
(転換)
週末、僕は新幹線に乗り、岩手県へと向かった。目的地は、記事に書かれていた動物園。園長に会うアポイントメントは取っていなかった。それでも、どうしても、彼の姿を、彼の言葉を、直接感じたかったのだ。
動物園に着くと、想像以上に閑散としていた。冬の寒さが厳しいため、訪れる人は少ないのだろう。僕は、受付で園長の居場所を尋ねた。受付の女性は、少し困った顔をしたが、快く教えてくれた。
園長は、クマの檻の前で、一人で立っていた。彼は、年配の男性で、顔には深い皺が刻まれていた。しかし、その目は、まるで子供のように、キラキラと輝いていた。
僕は、思い切って園長に話しかけた。「あの、すみません。記事を読んで、どうしてもお話を聞きたくて、来ました。」
園長は、少し驚いた顔をしたが、すぐに笑顔で応じてくれた。「ああ、記事を読んでくれたんだね。ありがとう。」
僕は、自分の仕事の悩み、将来への不安を、園長に打ち明けた。園長は、黙って僕の話を聞いてくれた。そして、最後に、こう言った。
「君の仕事は、無意味なんかじゃない。君の言葉は、誰かの心を動かす力を持っている。それを信じて、自分の仕事を大切にしなさい。」
園長の言葉は、僕の心に深く響いた。自分の仕事は、誰かの心を動かす力を持っている。そう信じることで、僕は再び、自分の仕事に誇りを持つことができた。
園長は、麻酔吹き矢について、詳しく話してくれた。麻酔吹き矢は、クマを傷つけることなく、安全に捕獲するための、重要な道具だ。しかし、麻酔吹き矢を使いこなすためには、高度な技術と、クマに対する深い理解が必要だ。
「麻酔吹き矢は、ただの道具じゃない。クマとの対話なんだ。」園長は、そう言った。
園長は、クマの生態を熟知していた。クマの性格、行動パターン、体調の変化。彼は、クマのすべてを理解しようと努めていた。
「クマは、怖いだけの生き物じゃない。臆病で、繊細で、そして、とても賢い生き物なんだ。」園長は、そう言った。
僕は、園長の言葉を聞いて、ハッとした。僕は、自分の仕事ばかりに気を取られ、目の前の人々のことを、何も見ていなかった。クライアントの要望ばかりを聞き入れ、その奥にある、本当の思いに気づこうとしていなかった。
(結末)
僕は、園長に深く感謝した。園長との出会いは、僕の人生を変えるほどの、大きな出来事だった。
帰りの新幹線の中で、僕は、自分の仕事に対する考え方を、改めて見直した。自分の仕事は、企業の利益を追求するだけでなく、人々の心を豊かにする力を持っている。それを信じて、自分の言葉で、人々に感動を与え、笑顔を届けたい。
そして、いつか、僕も、誰かの背中を押せるような、そんな存在になりたい。園長のように、自分の技術を後世に伝え、人々の安全を守るために、貢献したい。
2026年1月18日。あの日のカフェラテの味は、少し苦かったけれど、僕は、その苦さを、決して忘れないだろう。それは、僕が、自分の人生を、真剣に生きることを決意した、大切な思い出なのだから。
岩手の空は、都会の空よりもずっと広く、澄み切っていた。園長の背中は、夕日に照らされ、大きく見えた。僕は、小さく呟いた。「園長、ありがとうございます。」
そして、僕は、ぼやけていた未来の輪郭を、少しだけ、はっきりと見ることができたような気がした。
※このエッセイは、Togetterのまとめから着想を得て創作されたフィクションです。
📚 あわせて読みたい







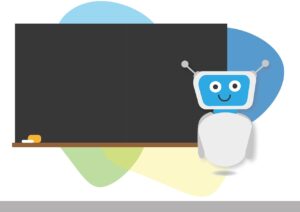



コメント